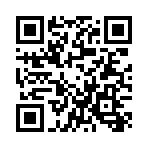2011年03月14日
役員会
明日午前、議員会館にて議連役員会を開催します。
AM9時半より 長島衆議院議員事務所にて
(議連が超党派であることの意義を、あらためて実感している次第です。
挙国一致の現状で、あるべき形でした。)
AM9時半より 長島衆議院議員事務所にて
(議連が超党派であることの意義を、あらためて実感している次第です。
挙国一致の現状で、あるべき形でした。)
Posted by 災害ボランティア議員連盟 at 12:38│Comments(4)
│活動報告
この記事へのコメント
長島会長の事務所です。
これから議連としての提言をまとめ、午後提出の運びとなりました。
国会議員会員の集まりも急遽行います。
細川、帰宅があやうい・・・。
どっちにいても涙涙で動いています。
これから議連としての提言をまとめ、午後提出の運びとなりました。
国会議員会員の集まりも急遽行います。
細川、帰宅があやうい・・・。
どっちにいても涙涙で動いています。
Posted by 事務局細川 at 2011年03月15日 11:11
ふくい災害ボランティアネットワークの先遣隊の仲間からの情報
看護師 Kさんからの生情報を転載します。
お疲れさまです。今日は名取と岩沼に入りました。避難所スタッフは圧倒的に不足です。ほとんどの支援者が家を流されたり家族を亡くしたりしていてご自分が大変なのに人や物がなく泣きながら活動しています。避難所の世話人や被災者と行政との間に温度差がありすぎます。避難所の格差が大きいです。しかし行政も被災者の声への対応に限界があるようです。6日目にもなると双方ともかなりイラだってきています。食料もまだおにぎりとパンだけの二食です。物資不足です。紙おむつ.下着.ホッカイロマスク.ミルク.哺乳瓶トイレットペーパー.ティッシュ.割り箸.紙皿.スプーン.生理用品.カットバン.体温計.手指消毒薬.食料.歯ブラシ.電池.ディスポ携帯充電器などまだまだです。寒い中で毛布一枚なのでインフルエンザや下痢など感染症胃腸疾患が増えています。名取もボランティアセンターが立ち上がっていますが公にしていません。資金がないので物品の準備ができず各
地域で話しあっているが全国のボランティアを受け入れる準備の見通しがたたないところば
かりです。仙台など数ヶ所心配しながらの開設です。家は泥だらけでボランティアのニーズはかなり高く早く入って欲しいです。これからの1日1日が精神的に限界になって行きます。とにかくガソリンです。夜中から並んでもガソリンが入手できなくなっています。ガソリンスタンドも営業中止か制限がかかり緊急車両だけ早いのでトラブルになっています。ガソリンがなんとかならないと移動もできず大変です。子ども達も学校再開目処たつかどうか避難所で塾はやっています。大変です。石巻も大船渡も大変で岩手に様子見にも行けません。
看護師 Kさんからの生情報を転載します。
お疲れさまです。今日は名取と岩沼に入りました。避難所スタッフは圧倒的に不足です。ほとんどの支援者が家を流されたり家族を亡くしたりしていてご自分が大変なのに人や物がなく泣きながら活動しています。避難所の世話人や被災者と行政との間に温度差がありすぎます。避難所の格差が大きいです。しかし行政も被災者の声への対応に限界があるようです。6日目にもなると双方ともかなりイラだってきています。食料もまだおにぎりとパンだけの二食です。物資不足です。紙おむつ.下着.ホッカイロマスク.ミルク.哺乳瓶トイレットペーパー.ティッシュ.割り箸.紙皿.スプーン.生理用品.カットバン.体温計.手指消毒薬.食料.歯ブラシ.電池.ディスポ携帯充電器などまだまだです。寒い中で毛布一枚なのでインフルエンザや下痢など感染症胃腸疾患が増えています。名取もボランティアセンターが立ち上がっていますが公にしていません。資金がないので物品の準備ができず各
地域で話しあっているが全国のボランティアを受け入れる準備の見通しがたたないところば
かりです。仙台など数ヶ所心配しながらの開設です。家は泥だらけでボランティアのニーズはかなり高く早く入って欲しいです。これからの1日1日が精神的に限界になって行きます。とにかくガソリンです。夜中から並んでもガソリンが入手できなくなっています。ガソリンスタンドも営業中止か制限がかかり緊急車両だけ早いのでトラブルになっています。ガソリンがなんとかならないと移動もできず大変です。子ども達も学校再開目処たつかどうか避難所で塾はやっています。大変です。石巻も大船渡も大変で岩手に様子見にも行けません。
Posted by 議連 副会長 東角 at 2011年03月17日 01:48
続 先遣隊のGさんより
今日は、災害対策本部ミーティング、地域福祉課(ボランティア、仮設住宅対応)、緊急物資センター現場、岩手県社協、盛岡市避難所、に行ってきました。
①物資関係
・岩手県では企業、団体、他行政からの物資しか受け付けていません。
物資はかなり集まっていますが(まだまだ少ないですが)、被災地への配送がスムーズにいっていません。
県の物資センターから被災がひどい11市町へ物資を届けています。(それ以外の市町村は独自で対応)
ようやく道路が復旧し始めているので、10トントラックで物資を運ぶことができはじめました。(以前は4トン車)しかし、11市町の拠点から各避難所への配送が滞っています。問題は燃料不足、そして人手不足です。
②ボランティアセンター
・岩手県社協ではボランティアを受け付けていません。盛岡市社協はボランティアを受け付け始めました。
ただ、盛岡市指定避難所が岩手県社協が入っている施設のため、岩手県社協も同時にボランティア受付をしています。
・今後の対応ですが、現在被害が大きかった市町村の状況把握を県社協が行っている状況です。
特に大槌町、陸前高田市は全社協職員が消息不明といった状態です。社協が消えた状態です。
その後の方向ですが、4地区に分けボランティアセンターを立ち上げます。
住田町に拠点
対象エリア 陸前高田市、大船渡市
遠野町に拠点
対象エリア 釜石市、大槌町
宮古市旧新里村に拠点
対象エリア 宮古市、山田町
久慈市に拠点
対象エリア 岩手県の北部の町村(比較的被害が少ない)
この4拠点にセンターを設けてボランティアを受け入れていく。ということです。
今後の課題としては、4拠点の支援体制をいかに早く構築していくかです。
しかし、燃料の安定供給が実現し、当面の自衛隊による活動(人命救助と瓦礫処理)が終了が当面の課題です。
ボランティアセンターの役割としては、物資と避難所対応ですが、これも燃料の安定供給がないと受け入れは非常に難しいですね。
本格的な活動が開始されるまでのセンター構築にぜひとも関わり、地元とも信頼関係を今から作る必要があります。
明日(17日)は県社協の方々と被災地(陸前高田市、大船渡市、釜石市、大槌町等)の調査に入ります。
今日は、災害対策本部ミーティング、地域福祉課(ボランティア、仮設住宅対応)、緊急物資センター現場、岩手県社協、盛岡市避難所、に行ってきました。
①物資関係
・岩手県では企業、団体、他行政からの物資しか受け付けていません。
物資はかなり集まっていますが(まだまだ少ないですが)、被災地への配送がスムーズにいっていません。
県の物資センターから被災がひどい11市町へ物資を届けています。(それ以外の市町村は独自で対応)
ようやく道路が復旧し始めているので、10トントラックで物資を運ぶことができはじめました。(以前は4トン車)しかし、11市町の拠点から各避難所への配送が滞っています。問題は燃料不足、そして人手不足です。
②ボランティアセンター
・岩手県社協ではボランティアを受け付けていません。盛岡市社協はボランティアを受け付け始めました。
ただ、盛岡市指定避難所が岩手県社協が入っている施設のため、岩手県社協も同時にボランティア受付をしています。
・今後の対応ですが、現在被害が大きかった市町村の状況把握を県社協が行っている状況です。
特に大槌町、陸前高田市は全社協職員が消息不明といった状態です。社協が消えた状態です。
その後の方向ですが、4地区に分けボランティアセンターを立ち上げます。
住田町に拠点
対象エリア 陸前高田市、大船渡市
遠野町に拠点
対象エリア 釜石市、大槌町
宮古市旧新里村に拠点
対象エリア 宮古市、山田町
久慈市に拠点
対象エリア 岩手県の北部の町村(比較的被害が少ない)
この4拠点にセンターを設けてボランティアを受け入れていく。ということです。
今後の課題としては、4拠点の支援体制をいかに早く構築していくかです。
しかし、燃料の安定供給が実現し、当面の自衛隊による活動(人命救助と瓦礫処理)が終了が当面の課題です。
ボランティアセンターの役割としては、物資と避難所対応ですが、これも燃料の安定供給がないと受け入れは非常に難しいですね。
本格的な活動が開始されるまでのセンター構築にぜひとも関わり、地元とも信頼関係を今から作る必要があります。
明日(17日)は県社協の方々と被災地(陸前高田市、大船渡市、釜石市、大槌町等)の調査に入ります。
Posted by 議連 副会長 東角 at 2011年03月17日 01:50
15日開催の議連臨時会議で決議された事に基づく提言書(案)
この度の「東北地方太平洋沖地震」における復旧・復興支援のために日本国民全てが、被災者と同様の痛みを感じ、国難として捉え、日本再生のために歩みださなければなりません。
そのための第一歩として、災害ボランティア活動があると考え、私たち議連としては本来の目的である災害ボランティア活動の環境整備について提言を致します。
今後、ある程度の交通インフラやエネルギーインフラが整った後に想定される災害ボランティア活動
■ 第一段階:物資ボランティア
・被災地に届けられた支援物資の拠点基地での搬入受入・管理・搬出
・避難所などへの配送やニーズ把握
■ 第二段階:避難所運営支援
・被災直後より避難所運営に当たって、疲れが出始めている行政(教職員含
む)・社協・自治会・被災者自身等の方々と協働する生活支援
■ 第三段階:復旧活動支援
・危険度判定・罹災証明が出たイエローゾーンにある民間建物・敷地及び公
園などの住民自治の管理下にある施設の片付けなどの支援。
災害ボランティア活動にとって最も大事な視点
被災地に支援漏れのない支援(支援差が出ない支援)
マスコミ報道・交通アクセス・地理的問題などの原因で、過去「人・物・金・
情報」の流れに非常な偏りが発生してきている。
今回、広域大災害であるので、これまで以上に支援に差が生じることが懸念
される。
時が来たのでは
■ 余りにも、被災範囲が広域であるがためか、被災地での活動リスクを考えすぎているためか、ボランティアの流入抑制が進んでいるように思える。これでは、生きている被災者に絶望感を与えるばかりである。早急に民の力を信じボランティアより元気を与えることをスタートさせながら国が調整を図るやりかたをしないと被災者は、疲弊するばかりである。
提 言
1.ブロック単位の支援体制を国の主導で作る必要がある。
被災地以外の自治体に呼び掛ける(指示する)必要あり(別紙図参照)
・被災地以外の自治体は、どこに支援すればいいか迷っている。
・支援漏れがないようにする必要がある。
・同一自治体の国民が継続して支援する事によって被災者の安心度が高まる。
・支援する側も同じブロックということで連携が取りやすい。
2.避難所支援のスタッフ配置と物資支援は至急行う必要あり。
・各種先遣隊からの報告では、避難所のスタッフが圧倒的に不足している。
物資(燃料含む)不足、生活インフラの絶対的不足という危機的メッセー
ジがあとを絶ちません。
・行政が行うべき医師・介護・看護・保育等のケア専門職の配置や教育者の
配置を早急に行う必要があります。
3.中央プラットフォームの設置が必要。
・情報の一元化(収集・分析・配信)
・復興へ向けた施策づくり
・避難所⇔最前線VC⇔県域拠点VC⇔中央プラットフォーム
4.協働のありかたについての基本指針を国が作る。
・行政(教職員含む)・社協・自治会・被災者自身等の方々とボランティアと
の協働のための基本指針をつくる。
(将来への自治再興・生業復活のための足掛かりとする)
5.ボランティアから雇用創出を行うという観点をもった政策立案
を行う。
・未就業の若い世代に支援を行いボランティア活動に携わってもらう
6.政治色が出ない(超党派)挙国一致体制で進める。
以上 国難を一億総ボランティアで解決していくために緊急提言(第一次)をする。
添付資料
ブロック別対応の枠組と中央プラットフォームのイメージ図
この度の「東北地方太平洋沖地震」における復旧・復興支援のために日本国民全てが、被災者と同様の痛みを感じ、国難として捉え、日本再生のために歩みださなければなりません。
そのための第一歩として、災害ボランティア活動があると考え、私たち議連としては本来の目的である災害ボランティア活動の環境整備について提言を致します。
今後、ある程度の交通インフラやエネルギーインフラが整った後に想定される災害ボランティア活動
■ 第一段階:物資ボランティア
・被災地に届けられた支援物資の拠点基地での搬入受入・管理・搬出
・避難所などへの配送やニーズ把握
■ 第二段階:避難所運営支援
・被災直後より避難所運営に当たって、疲れが出始めている行政(教職員含
む)・社協・自治会・被災者自身等の方々と協働する生活支援
■ 第三段階:復旧活動支援
・危険度判定・罹災証明が出たイエローゾーンにある民間建物・敷地及び公
園などの住民自治の管理下にある施設の片付けなどの支援。
災害ボランティア活動にとって最も大事な視点
被災地に支援漏れのない支援(支援差が出ない支援)
マスコミ報道・交通アクセス・地理的問題などの原因で、過去「人・物・金・
情報」の流れに非常な偏りが発生してきている。
今回、広域大災害であるので、これまで以上に支援に差が生じることが懸念
される。
時が来たのでは
■ 余りにも、被災範囲が広域であるがためか、被災地での活動リスクを考えすぎているためか、ボランティアの流入抑制が進んでいるように思える。これでは、生きている被災者に絶望感を与えるばかりである。早急に民の力を信じボランティアより元気を与えることをスタートさせながら国が調整を図るやりかたをしないと被災者は、疲弊するばかりである。
提 言
1.ブロック単位の支援体制を国の主導で作る必要がある。
被災地以外の自治体に呼び掛ける(指示する)必要あり(別紙図参照)
・被災地以外の自治体は、どこに支援すればいいか迷っている。
・支援漏れがないようにする必要がある。
・同一自治体の国民が継続して支援する事によって被災者の安心度が高まる。
・支援する側も同じブロックということで連携が取りやすい。
2.避難所支援のスタッフ配置と物資支援は至急行う必要あり。
・各種先遣隊からの報告では、避難所のスタッフが圧倒的に不足している。
物資(燃料含む)不足、生活インフラの絶対的不足という危機的メッセー
ジがあとを絶ちません。
・行政が行うべき医師・介護・看護・保育等のケア専門職の配置や教育者の
配置を早急に行う必要があります。
3.中央プラットフォームの設置が必要。
・情報の一元化(収集・分析・配信)
・復興へ向けた施策づくり
・避難所⇔最前線VC⇔県域拠点VC⇔中央プラットフォーム
4.協働のありかたについての基本指針を国が作る。
・行政(教職員含む)・社協・自治会・被災者自身等の方々とボランティアと
の協働のための基本指針をつくる。
(将来への自治再興・生業復活のための足掛かりとする)
5.ボランティアから雇用創出を行うという観点をもった政策立案
を行う。
・未就業の若い世代に支援を行いボランティア活動に携わってもらう
6.政治色が出ない(超党派)挙国一致体制で進める。
以上 国難を一億総ボランティアで解決していくために緊急提言(第一次)をする。
添付資料
ブロック別対応の枠組と中央プラットフォームのイメージ図
Posted by 議連 副会長 東角 at 2011年03月17日 01:52